- “皮”と”革”の違いがわかる
- “鞣し”の意味と方法を知ることができる

突然だけど、皮と革は違うって知ってた??
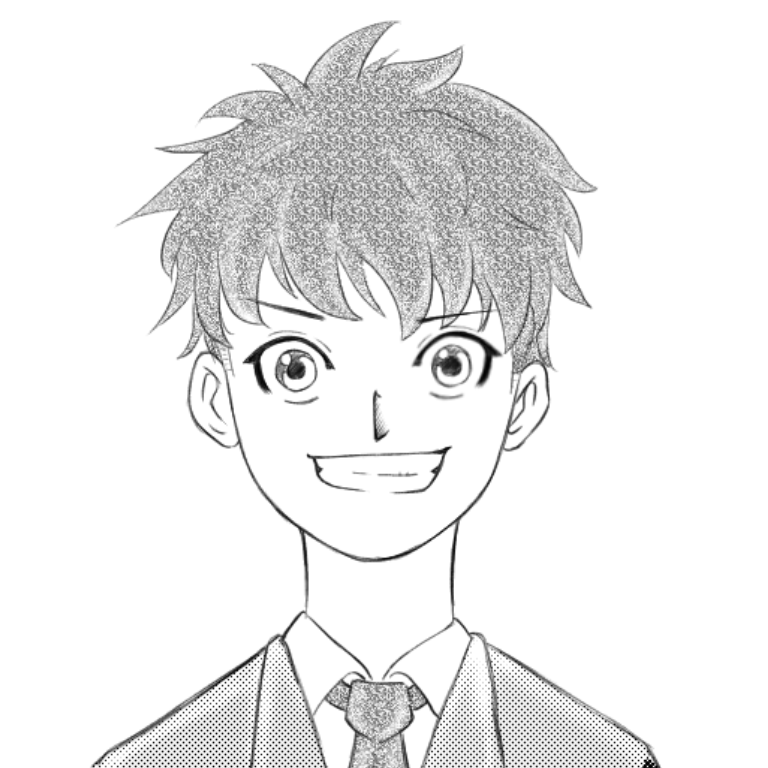
えぇっ?!同じじゃないんですか??
革製品に興味を持つ方は知ってましたか?同じモノと思われるかもしれませんが、皮と革では言葉が指すモノに違いがあります。
- 「皮」⇒動物の体毛や肉片がまだ残っている状態の皮(=原皮)
- 「革」⇒鞣し工程によって皮を腐りにくく乾燥させにくい状態に加工した皮
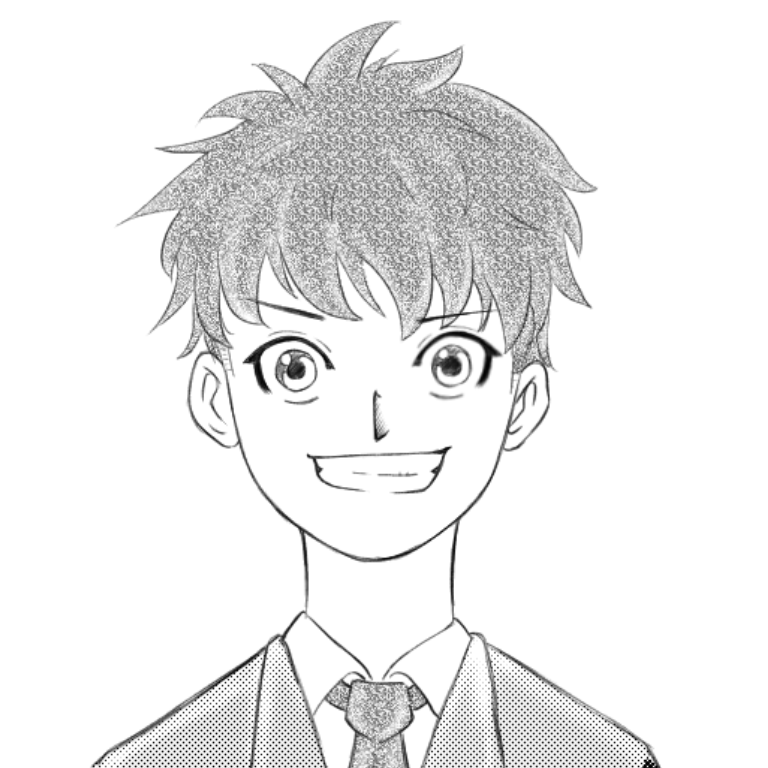
なるほど!皮を腐らないように加工したものが革なんだ!
…で、「鞣し」ってなんですか?あと読み方もわからない…。
「鞣し」=「なめし」と読みます。革製品に興味を持つとよく耳にする言葉でしょう。しかし具体的に鞣し工程がどんなものなのかピンとこない人もいるのではないでしょうか?
そこで今回は皮を革に変える鞣しについてまとめてみました(^^♪
- 鞣しの役割を説明
- 主な3つの鞣し方法とは?
- 鞣し方法の違いによる仕上がりの特徴はあるのか?
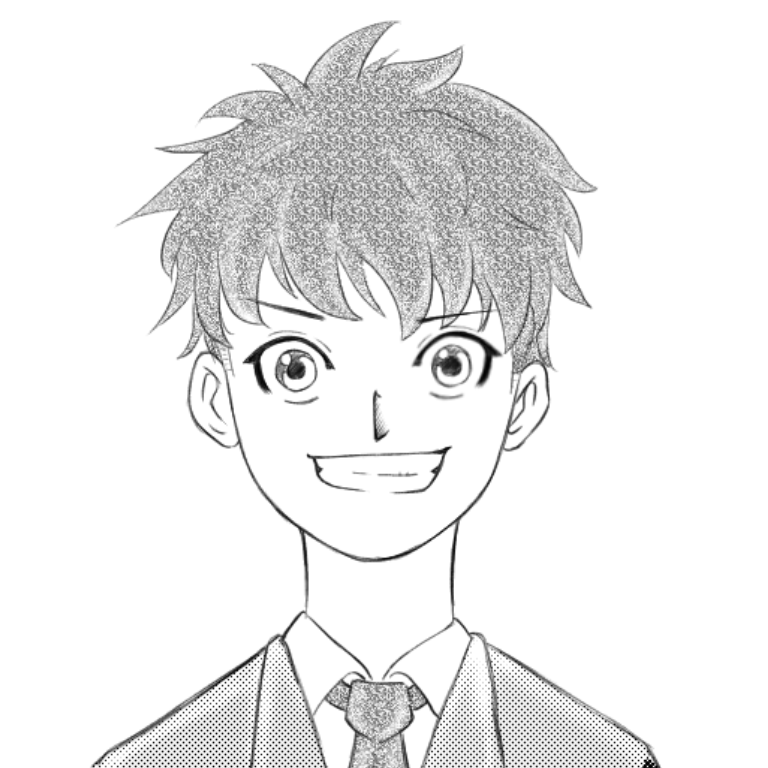
Yoshiは、5年間で3度の転勤をきっかけにミニマリストになった会社員。ミニマリスト歴4年目に突入。
趣味の靴磨きで人生が変わったことから、靴磨きの楽しみ方をYouTubeでも発信しています!
【鞣すってなんぞや?】皮を革に変える鞣しとは?
鞣しとは、皮を腐敗させないように加工し、実用性の付加価値を与える工程です。
というのも原皮のままでは腐りやすく硬くなってしまうので実用性のないモノになってしまうためです。そのため鞣しは、はるか昔から様々な方法で行われてきました。

原皮を燻したり、人の唾液で鞣してみたりと様々な方法が世界各地で行われてきたみたい。
ゆえに人類最初の化学処理といも言われているんだって!
つまり鞣しとは、皮に実用性を与えて革に変える錬金術のような役割と覚えよう!
鞣し方法の種類
鞣しの方法は現在3つに分けることができます。
- 植物タンニン鞣し
- クロム鞣し
- 混合鞣し
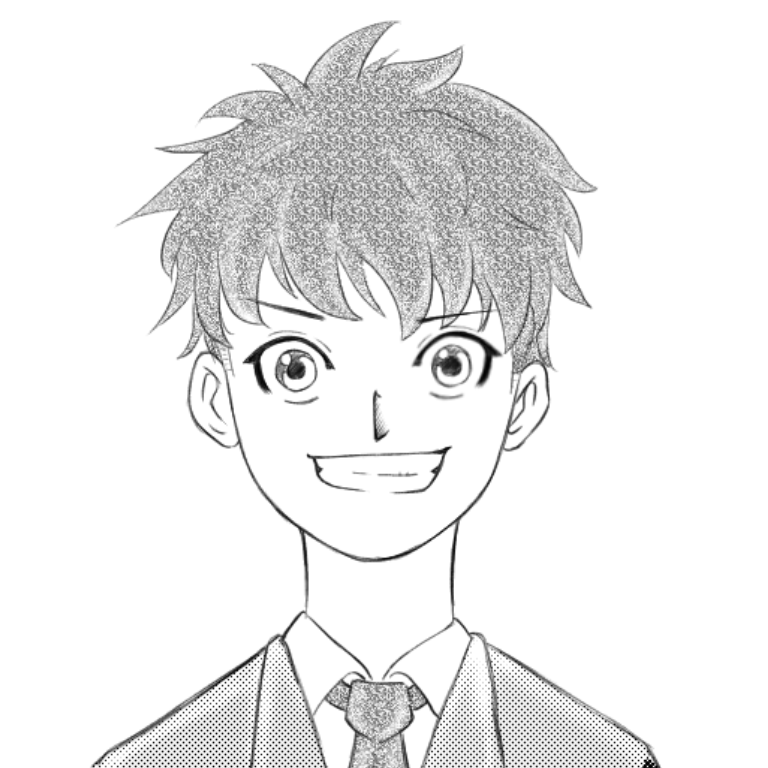
な…なんだかよくわからん言葉が出てきたな(~_~;)
でも大丈夫です。これらの違いは主に植物で鞣すか鉱物で鞣すかの違いです。詳しく鞣しの方法や特徴を見ていきましょう。
植物タンニン鞣し
- タンニン(植物から抽出)
- 樹皮や葉から抽出
- 濃度の違うタンニンが入ったピット(桶槽)に漬け込む
- 数日おきに漬け変えて1か月~3か月など長期間かかる
- 頑丈で摩耗に強く伸びにくい
- 形状記憶にも優れている
- 色落ちしやすい
時間をかけて徐々に革へ仕上げていく鞣し方法によって得られる革の特徴から、靴ではソールやヒールといった底材として使用されています。
クロム鞣し
- 三価クロム塩溶液
- 回転槽(ドラム)に原皮とクロム溶液を入れて回転させる。
- 6~12時間で鞣しが完了する
- 柔らかく弾力があり伸び安い
- 耐熱性もあり染色しやすい
19世紀に技術が出来上がった鞣し方法。植物タンニン鞣しとは違い、圧倒的に早い時間で鞣すことができるためコストがかからず大量生産に適した鞣し方法です。
摩耗しやすく頑丈さでは劣るので、靴ではアッパーに使われる。
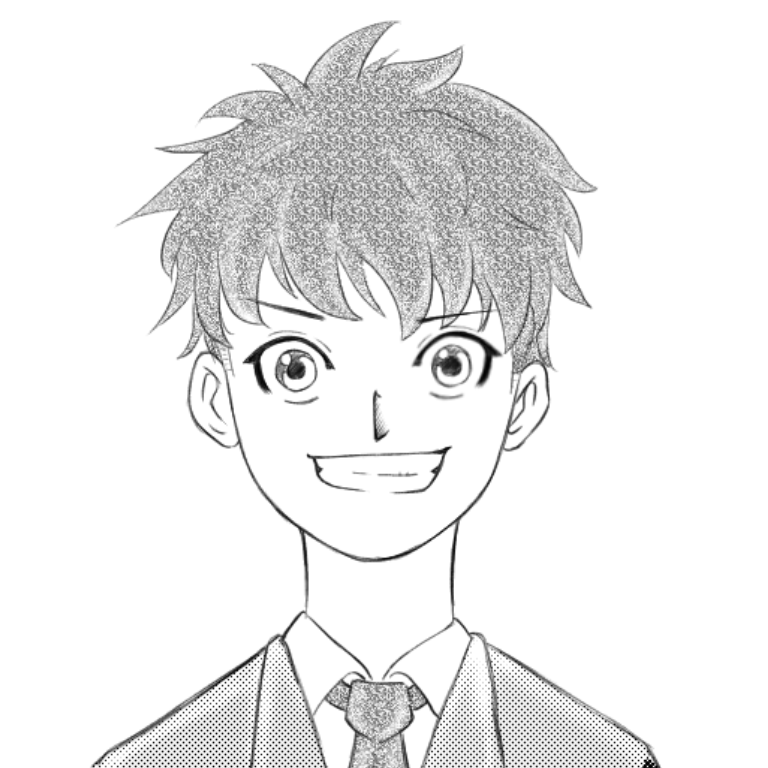
植物タンニン鞣しの革とクロム鞣しの革は、対極的な特徴になるんだね!
混合鞣し
- タンニン
- 三価クロム塩溶液
- 植物タンニン鞣しとクロム鞣し両方の鞣しを行う
- 植物タンニン鞣しとクロム鞣しの特徴のいいとこどり

クロム鞣しを先に行う場合は「コンビ鞣し」。
植物タンニン鞣しを先に行う場合は「逆コンビ鞣し」と呼びます!
まとめ:新たな鞣しも開発されていく
以上が皮から革へ変える鞣しのまとめと革の違いでした。
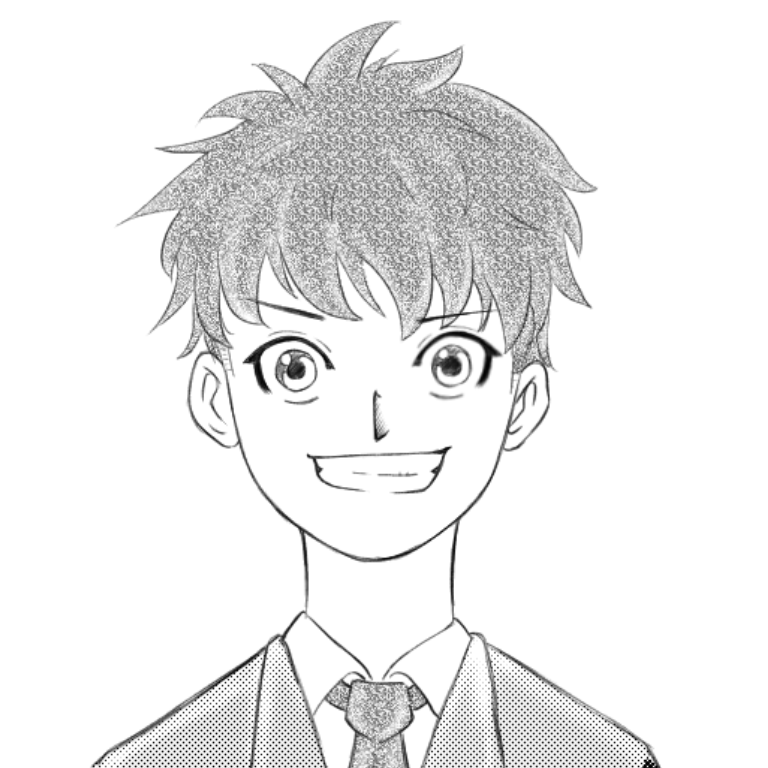
牛を皮にする年齢とかでもたくさんの違いがあったのに、鞣しかたでもこんなに違いが出るなんて…。
革って本当に奥が深い(;’∀’)

ただ、この鞣しについては環境の面から今後の生産について課題が山積みなんだ…。
クロム鞣しの鞣し材「三価クロム」はひとつ処理を間違えると有害な物質に変わる危険があり、また自然界に還りにくい成分でもあるようです。
近年の環境への関心が高まっていることから、クロム鞣しを得意としていたタンナーが相次いで廃業しています。
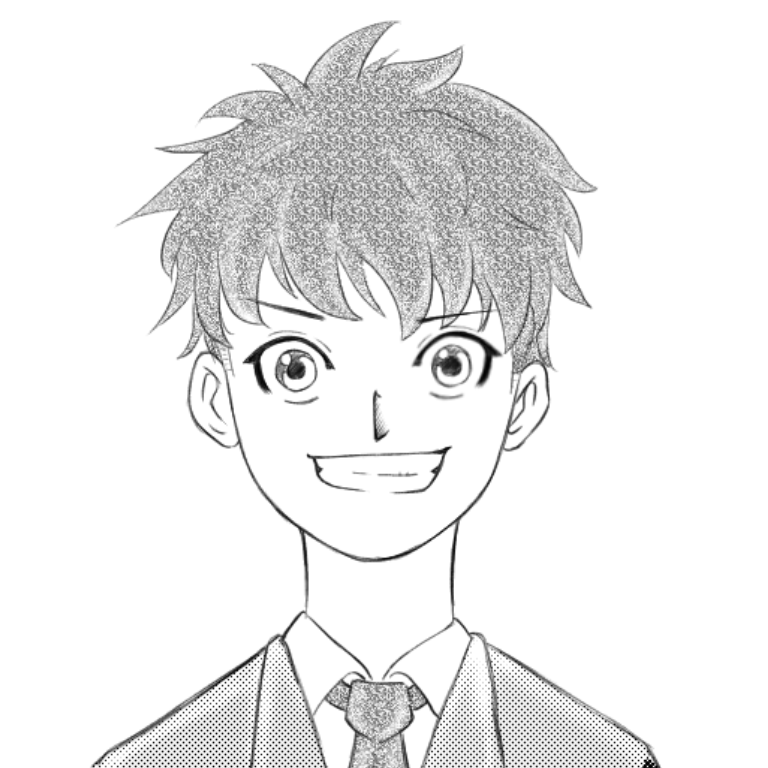
クロム鞣しの製造を改善して環境にアプローチしようとすると莫大なコストでとても経営が回らないのも理由のひとつ。
クロム鞣しの特徴を持つような新たな鞣しも今後登場してくるかもしれませんね。
以上、Yoshiでした!

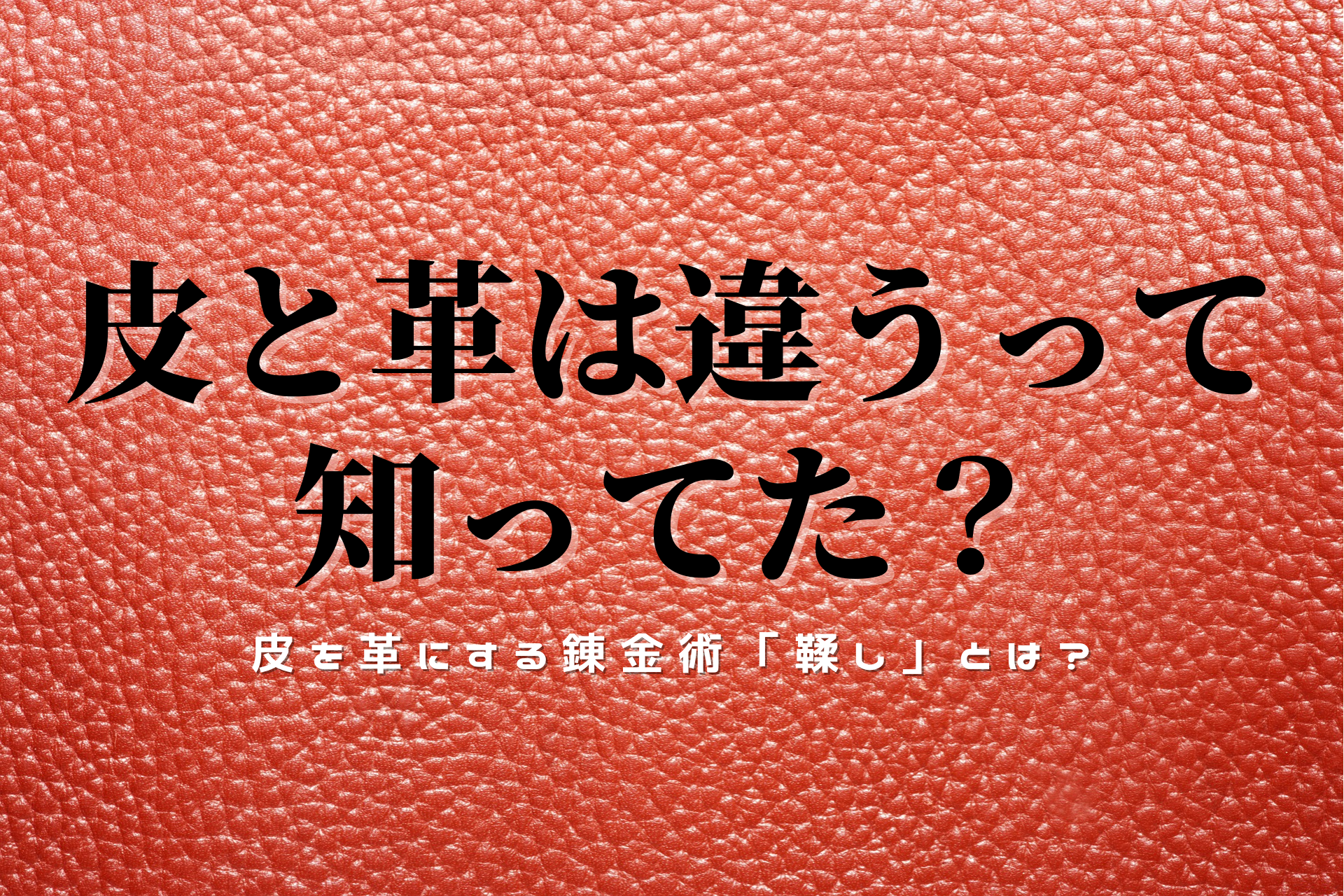



コメント